
弘法大師(空海)のおわす高野山へ
高野山で一泊するので、ゆっくりの出発
🚃南海高野線の「橋本駅」から「極楽橋駅」までは約40分
🚋「高野山駅」までは、ケイブルカーで約5分
🌂小雨が降っていたので、運慶の『八大童子立像』、快慶の『孔雀明王像』をゆっくり観ようと、🚌バスで「霊宝館」まで15分ほど
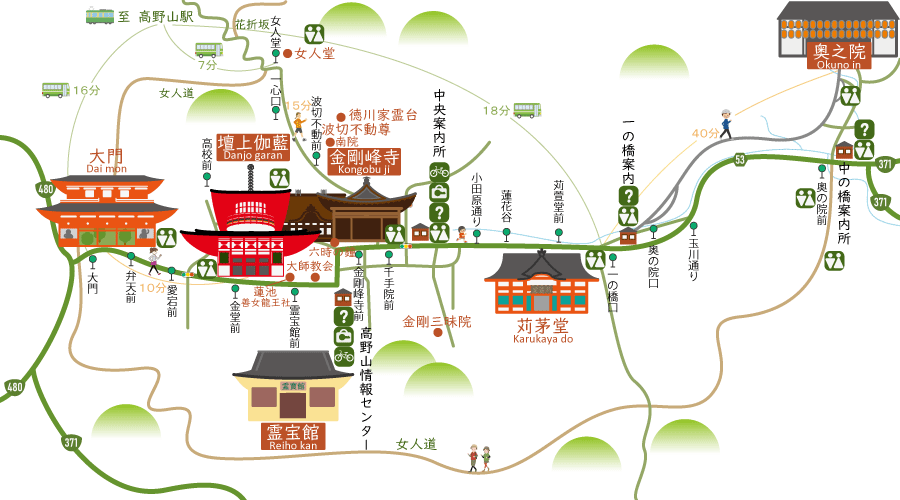
霊宝館(れいほうかん)

空海(くうかい)がもたらした密教
壁一面の大きな曼荼羅(まんだら)、『金剛曼荼羅(こんごうまんだら)』と『胎蔵曼荼羅(たいぞうまんだら)』が向かい合っている
どれもスゴイ
めったに、お目にかかれない弓で射る「天弓愛染明王像」
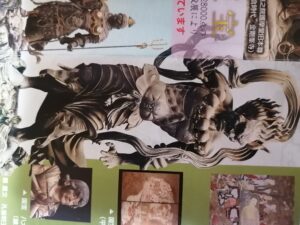
快慶の『深沙大将(じんじゃだいしょう)立像』
玄奘(げんじょう)三蔵がインドに行く途中、砂漠で玄奘を守った?!
毛は逆立ち
恐ろしい顔
骸骨(ガイコツ)の頭が連なるネックレス
両ヒザには🐘ゾウの頭
ヘソは人の顔?鬼の顔?
緻密でミスのない快慶の傑作
もちろん運慶の国宝『八大童子』はGOOD\(^o^)/
国宝の『涅槃図(ねはんず)』は修理中?なのか無かったのは残念
宿坊(しゅくぼう)に行く前に
「刈茅堂(かるかやどう)」に寄った
堂内には、『石童丸物語』の悲しい物語が額絵で、つづられている
阿字観(あじかん)
宿坊で
まずは「阿字観(あじかん)」と呼ばれる座禅(ざぜん)体験
梵字の「阿」を仏様と思い
一から十まで数える間、鼻で息を吸い、口から息を吐く・・・を繰り返す
目は仏像と同じ薄目で、自分の鼻先を見る
手は胎蔵大日如来(たいぞう だいにちにょらい)と同じ、右手を上に円を描き親指を押した形
足も右足が上で胡坐(あぐら)
背筋は真っすぐ
肩をポンなどなかった(;´∀`)
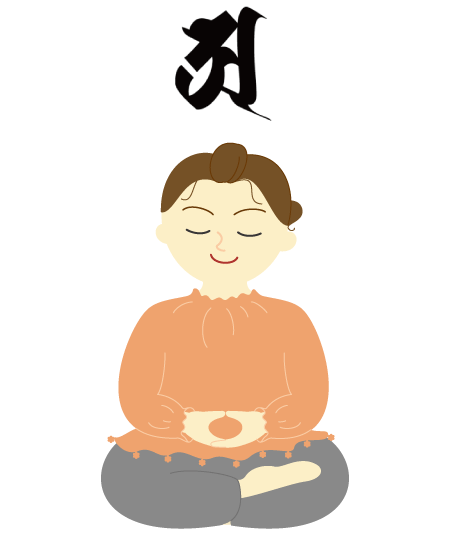
早い夕食
お坊さんが運んでくれる
お坊さんだけでなく、高野山高校の学生もアルバイト?
ごま豆腐などの「精進料理(しょうじん りょうり)

奥の院のナイトツアー
さあ、夜の7時からは
「奥の院(おくのいん)のナイトツアー」
石の墓や供養塔(くようとう)が立ち並ぶ中を1時間半、お坊さんがガイドしてくれる
雨も止んだ
自分だけだったらと不安だったが、15人ほどいてホッとした

橋は三つ、必ず手を合わせ一礼してから渡る
「一の橋(いちのはし)」を渡ると
まずは『数取地蔵(かずとりじぞう)』
参拝者が奥之院にお参りした回数を数え、その人が地獄に落ちそうになったら、閻魔(えんま)大王にとりなしてくれるのだとか・・・
「一の橋を渡ったら左側の道を進まなければ、このお地蔵さまに会えないから、次回もこの道を歩いてね」と・・・!
「中の橋(なかのはし)」の手前に、『明智光秀(あけちみつひで)』の供養塔が右手にある
何度、立て直してもヒビが入る
明智光秀の反乱で死んだ織田信長(おだのぶなが)のうらみ!らしい(*_*;
次の日の日中確かめた

「どうして供養塔の前に鳥居(とりい)があるの?」の質問が・・・
もともと日本は神国だからだそうだ
お寺の中に、よく鳥居を見かけます
神様にも見守ってもらっているのですね

最後は、三つ目の橋「御廟橋(ごびょうばし)」
空海が今もおわす場所へ
以前は、この橋はなく、空海さまにお会いするには、川の中を歩き、身を清めて会いに行ったらしい

今は、橋の手前の『水向地蔵(みずむけ じぞう)』に水をかけ清い気持ちで
「御廟橋(ごびょうばし)」に礼をしてから会いに
そして、橋の手前で写真は撮れるが、橋からは写真は禁止!
『燈籠堂(とうろうどう)』は、朝の6時から夕方5時半まで
裏に周り、祠(ほこら)の前で、お坊さんがお経を唱えてくれている間に
願い事を・・・たっぷり
「御廟橋(ごびょうばし)」を出たところで解散
お坊さんについて行くとバスで帰ることが出来る
あの暗い中を一人ぼっちでは帰れない
新らしくした宿坊だが、なかなか寝付けなかった
朝は6時半から勤行(ごんぎょう)
3人のお坊さん
真ん中の本尊(ほんぞん)の前に座るお坊さんは一番えらいようで、ずっと座っていた
左側のお坊さんは、主にお経を唱えていた
右側のお坊さんは、お経とシンバルのようなものを、時々鳴らし
「お焼香してください」と教えにきたりと
動作には一つ一つ決まりがあるらしく、へ~ ・・・
左側のお坊さんと右側のお坊さんは、大きな声でお経を唱えるが
違う所で息継ぎをして、また合わせる・・を繰り返し へ~
おもしろい
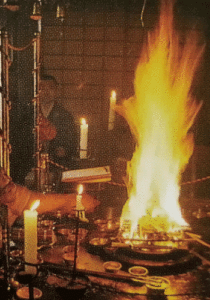
そして別棟で
護摩(ごま)祈祷を
所作(しょさ)というのだろうか?
数珠(じゅず)をこすったり
金色の小さな鉢がたくさんあり、場所を入れ替えたり
火に(何の粉?なにもない?)指でまいたり
小さなシャクでまいたり
護摩木(ごまき)を交互に置き
少し大きめの木を組み、次に小さめの木を組み合わせ
ろうそくの火を移す
炎が少しずつ大きくなる
目の前で炎が、ピチピチと音をたて、火の粉に 火の筋も・・・
心が、ゆさぶられる
勤行の時の右側のお坊さんが、護摩(ごま)の間中、大声でお経を唱え続けていた(@_@;)
お疲れ様です!
護摩のお坊さんも男前!
男前だらけ!
昨日の阿字観(座禅)の時から、時折しゃべっていた女性
「煩悩(ぼんのう)を払いに高野山に来たのに男前のお坊さんだらけ!よけい煩悩がメラメラ!」って
(-。-)y-゜゜゜
「また来よ」
もう一度、奥之院の『燈籠堂(とうろうどう)』まで歩いた
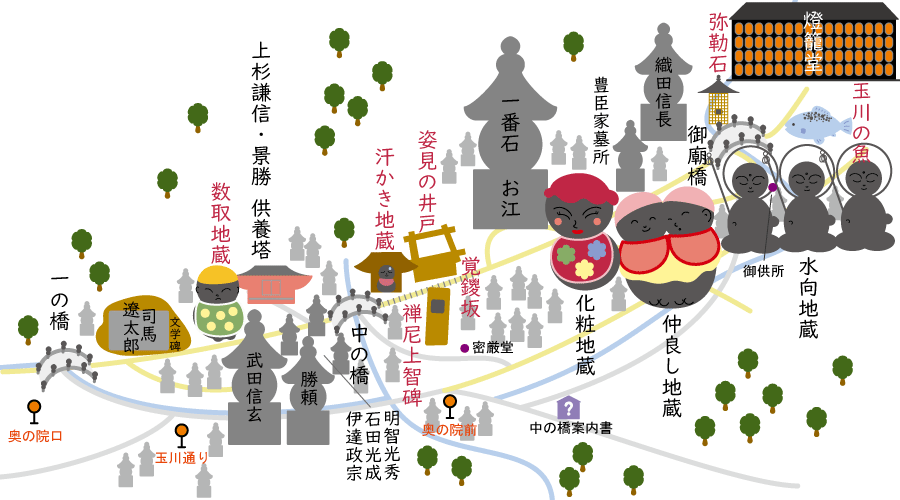
『燈籠堂』の中でも、護摩祈祷(ごまきとう)をしていた
お坊さんが、おまんじゅうとグレープフルーツを指差して
「お供物をどうぞ」と
タダ!
昔ながらの白いまんじゅうだが
こしあんの中に粒あんが入って砂糖も控えめ
おいしかった
10時半ごろに、御陵橋の手前にいると、弘法大師に食事を運ぶ行事が見られるらしいが
バスの時間が・・・断念
永遠と続けてきた行事
そして、永遠とつづく・・・・・
太い杉の木に囲まれた高野山
山の中の盆地
清い空気が流れる
- 奥之院参道の入口にある一の橋 弘法大師空海が参詣者(さんけいしゃ)をここまで送り迎えしてくれるという伝承があるので、渡る前に一礼を
- 弘法大師の御廟を祀る聖地 奥の院参道は、一の橋から、中の橋、御廟橋(ごびょうぼし)を渡り、燈籠堂(とうろうどう)の奥に祀られる御廟まで、約2kmに渡って杉木立に包まれ、20万基以上の時代を超えた募碑や供養塔(くようとう)が立ち並ぶ
- 高野山を随筆『高野山管見』に描いた司馬遼太郎の文学碑が立つ 開創1200年を記念して建立された
- 向かって左が武田信玄(恵林寺殿)、右が息子の勝頼(法泉殿)の供養塔 好敵手だった上杉謙信の霊屋の向かいに立つ
- 戦国時代の武将、謙信と甥の景勝を供養する朱塗りの麗しい霊屋 信玄の供養塔を見下ろす高台に立っている
- 中の橋のたもとにあるお堂に祀られているお地蔵さま 水滴がついて汗ばんでいるように見えることから、人々の苦しみの身代わりになっているとの言い伝えが
- 汗かき地蔵の、そばにある井戸 水面をのぞいて自分の姿が見えなければ3年以内に命がなくなるとの伝説がある
- 中の橋から続く石段の坂道 この坂で転ぶと、3年以内に寿命が縮まる 石段の数は42(死に)を超える43段ある
- このお地蔵さまに化粧しておまいりする
- かわいい二体のお地蔵さま
- 本能寺の変に倒れた戦国武将、信長の供養塔 長らく場所が不明だったが、御廟橋(ごびょうばし)の近くにあると判明
- 玉川のほとりに奉納されたお地蔵さまや観音さま、お不動さまなどが並ぶ お供えした水向塔婆に水を手向けて、ご先祖の冥福を祈る
- この橋から奥は弘法大師の御廟がある霊域 服装を正し、一礼をしてから橋を渡ろう この先は私語を謹んで 写真撮影も禁止されている
- 橋板の裏に、それぞれの仏様の梵字が記されている
金剛峰寺(こんごうぶじ)

高野山真言宗の総本山

石庭の石が、でっかい!
壇上伽藍(だんじょうがらん)

多くの塔や、お堂が建っている
- 伽藍とは梵語のサンガ・アーラーマの音訳で、僧侶が集い修行をする閑静清浄な所という意味
- 1127年醍醐寺勝覚権僧正が白河上皇の御願により創建
- 丹生明神と高野明神を勧請し、高野山の守護神として祭った
- 根本大塔と対をなす重要な多宝塔 本尊の大日如来像は霊宝館に安置
- 大師が発願され、第二世真然大徳の代に完成 直径7尺、重量1.600貫(約6トン)
- 1159年、皇后であった美福門院得子が夫鳥羽上皇の菩提を弔うために創建
- 高野山一山の総本堂で、年中行事の大半がここで勤修される
- 一山の総門である大門に対して、伽藍の正門として南側入り口には中門が建つ 2015年に再建された
根本大塔(こんぽんだいとう)
 塔の中は
塔の中は
中央には、胎蔵大日如来(たいぞう だいにちにょらい)像
まわりの4体は金剛界の四仏
そのまわりに16本の太い柱に菩薩が描かれている
「笑菩薩」という、ほほえむ菩薩さま など
堂本印象(どうもと いんしょう)作
大門(だいもん)
 最後に大門
最後に大門
それぞれの宿坊に、秘仏もあるようだ
光臺院(こうだいいん)の宿泊者のみが見ることができる、快慶作の阿弥陀三尊(あみださんぞん)
南院(なんいん)の波切不動(なみきりふどう)は6月28日のみ開帳
明光院の赤不動尊画像は4月28日のみ拝観
龍光院の四面大日如来
などなど
奥の院での勤行も
またね!



