 瀬戸内一の景観!
瀬戸内一の景観!



常夜燈じょうやとう(一晩中、ともしておく灯)
雁木がんぎ(桟橋の船着場にある階段)
波止場はとば(波を防いで船を停泊させ、荷物の揚げおろしの通路)
焚場たでば(天然ドック 船を建造、修理、係留するための施設)
船番所跡ふなばんしょあと
ほぼ完全な形で現存しているのは「鞆の浦」だけ!




髪の毛がある お地蔵さんがいらっしゃる「小松寺」
ユニークですね。




由緒ある「沼名前神社」では、火祭りが催される。








「活気に溢れた町」と!
ちなみに、朝井まかて著『先生のお庭番』を読み、シーボルト事件の実情を知るきっかけになった。




電車
広島駅 JR山陽新幹線(25分~55分)
JR山陽本線(1時間45分)
→福山駅 トモテツバス→鞆の浦or鞆港(約30分)
車
広島IC 山陽自動車道(約95km)→福山東IC 国道182号線 南下(約35分)




鞆の浦(とものうら)観光名所
安国寺(あんこくじ)




桜の名所で「阿弥陀如来立像(あみだにょらいりつぞう)」と
「法燈国師座像(ほっとうこくしざぞう-臨済宗の僧)」が、
ライトアップされた桜の後ろで、優しく照らされている。
小烏神社(こがらすじんじゃ)




福島正則が『鞆の浦』の城下町を整備した際に鍛冶工を、この地域に集めて鍛冶屋町を造り、その中心にあたるのが『小烏神社』です。12月『ふいご祭り(鉄鋼祭)』が開かれます。
南北朝時代の古戦場でもありました。
沼名前神社(ぬまくま じんじゃ)




海上安全の「大綿津見命(おおわたつみのみこと)」を祀る『渡守(わたす)神社』と、無病息災を祈願する「須佐之男命(すさのおのみこと)」を祀る『祇園社』があり、鞆の人々に「ぎおんさん」と呼ばれ親しまれている。




日本でここだけの『鳥衾(とりぶすま-鳥の寝床)』が付いてますよ。
簡単に分解し移動できる、豊臣秀吉 遺愛の能舞台があります。
小松寺(こまつじ)




以降、足利尊氏の陣を構えたりと歴史に登場します。



龍馬の隠れ部屋 枡屋清右衛門宅(ますやせいえもんたく)




坂本龍馬ら海援隊士が乗った「いろは丸」と紀州藩の「明光丸」とが岡山県六島沖で衝突し、「いろは丸」が沈没するという事件が起きた。
この際、鞆港を訪れた龍馬が宿泊したのが「枡屋清右衛門宅」でした。



龍馬は階段のない2階の隠れ部屋に寝泊まりしたと伝えられており、暗殺の危機もかえりみず談判にのぞんだ覚悟がしのばれる。
対仙酔楼(たいせんすいろう)




江戸の後期の儒学者、頼 山陽(らい さんよう)が「山紫水明(さんしすいめい)自然の風景が清浄で美しいこと」の熟語を生み出した場所とされる建造物。
福禅寺(ふくぜんじ)の対潮楼(たいちょうろう)




座敷から観る瀬戸内海に浮かぶ島々は素晴らしく、朝鮮通信使から「日東第一景勝」と賞賛された。
万葉歌碑(まんよう かひ)
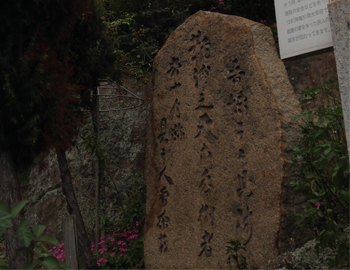
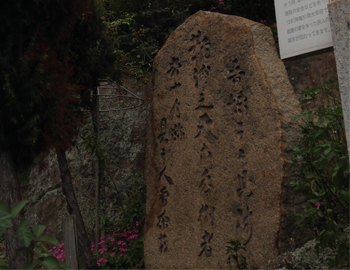


死別した妻を想う歌。
鞆の津の商家(とものつの しょうか)




主屋(おもや-家族が住む家)と土蔵(どぞう-倉庫)が隣り合って建っている。
黒壁に二階の白い縁取りの虫籠窓(むしこまど)が、かっこいい。



「鞆の産業は漁業と鉄工」だと、いろいろな場所で分かります。
大可島城跡(たいがしまじょうあと)圓福寺(えんぷくじ)・夾明楼(きょうめいろう)




南北朝時代から鞆の浦の拠点であり、戦国時代は村上水軍の一族は、ここを拠点として海上交通を支配した。
そして「いろは丸事件」の談判場所でした。



「夾明楼」は、圓福寺の座敷で、ここからの眺めは格別。
江戸時代を通して漢詩会や歌会、句会が催され、儒学者や風流人に愛されたそうな。
力石(ちからいし)




地蔵院(じぞういん)




歯がある「木造十一面観音立像」が安置されていて、歯の健康を守る仏様として信仰されている。
お地蔵さんが静かにいらしゃる空間も味わってください。
阿弥陀寺(あみだじ)




鞆一番の山門。
5年かけて完成させたピカピカ約5メートルの大仏
「丈六(じょうろく約4.85m)阿彌陀如来座像(あみだにょらいざぞう)」が鎮座。
医王寺(いおうじ)




山の中腹にあるので、鞆の浦の街並みや島々を眺めることができる。
岡本家長屋門(おかもとけ ながやもん)




明治のときの火災で、廃城の福山城の長屋門を買い取って店舗にしたそうな。
太田家住宅(おおたけ じゅうたく)・七卿落遺跡(しちきょうおち いせき)








七卿落ち1863年三条実美ら七人の公卿が、長州の手引きで都落ちする際に途中、鞆の浦に立ち寄り、憩ったのが太田家である。
とうろどう(文学資料館)




海中の亀腹型石積まで含めると10メートルを超す大きさで、日本一。
保命酒(ほうめいしゅ)




「瀬戸内の養命酒」と言われているが、医薬品ではない。江戸時代の保命酒は、主に公家や上級武士、豪商の高価なものだった。
最盛期は昭和初期ごろで、海外への輸出も行われていたが、太平洋戦争で品質低下と鞆町の衰退で生産は減少した。
パワースポット仙酔島(せんすいじま)








海岸線に沿った歩道を歩いていると、岩の色がさまざまに変化し驚き魅せられます。
アクセス
鞆港 徒歩3分→渡船場 船(5分)→仙酔島渡船場




ポニョのお父さんが海に立ってる
ポニョのお母さんが、ゆうゆうと漂ってる
そんなことも感じられます。
自然をたっぷり味わうハイキングコース




短い距離で、岩石、植物、鳥、伝説歴史が分かる
仙人コース
夕陽が沈むときは、特に美しい
弥山コース 3.5km(約1時間30分)
森林浴を味わえる
鳥の口コース 2.7km(約1時間)
天然記念物の断層や地層や岸壁が魅力的
