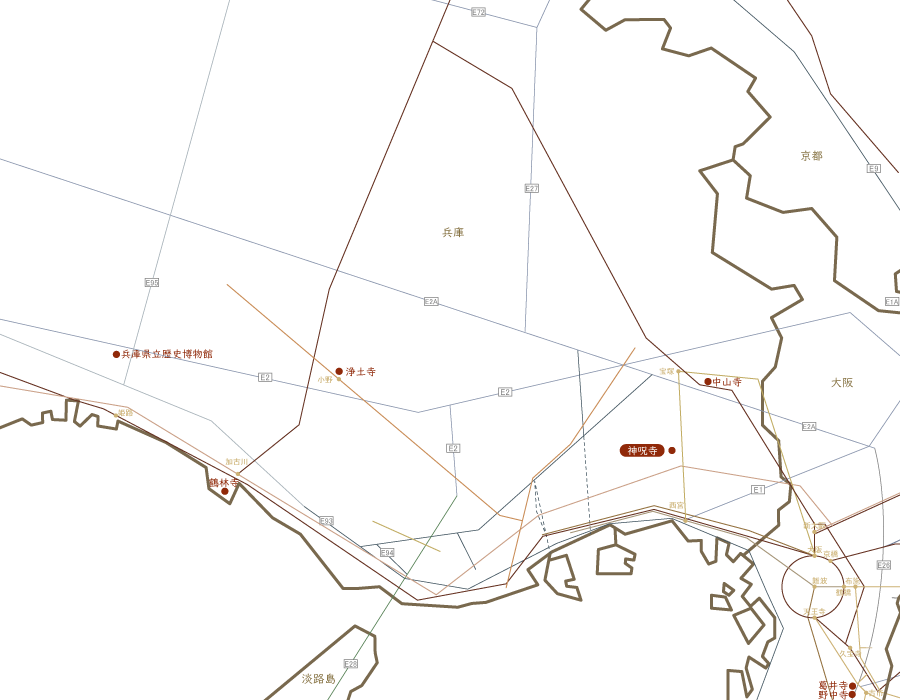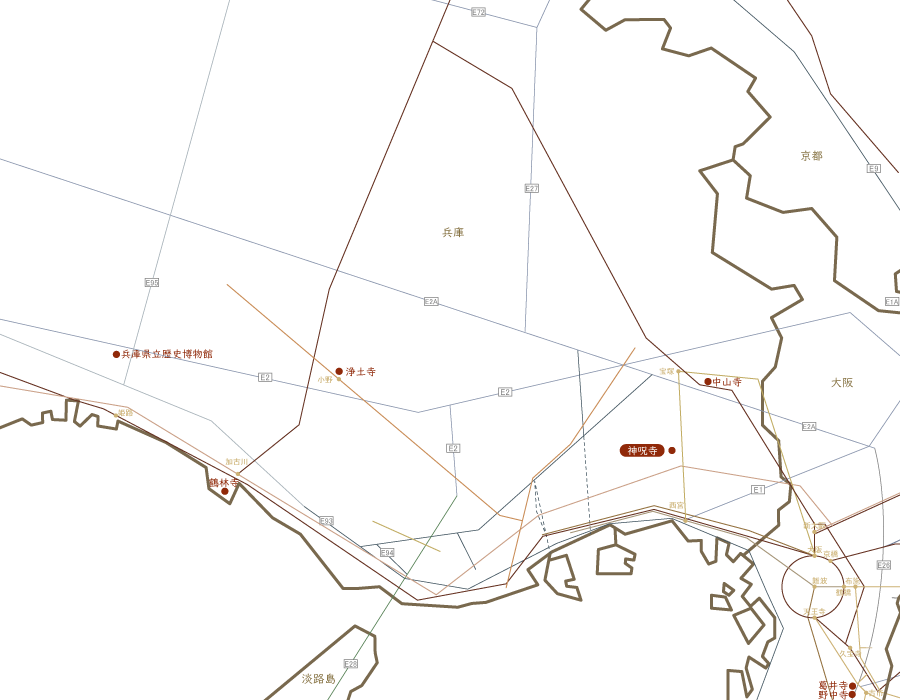阪神電鉄「西宮」駅を降りて
北側のバス乗り場に
目の前に「西まわり」のバスが?!
バスは動き出した
??何か?おかしい
10分発のはずが
停車するバス停を🔎
途中で違う!
車掌さんに聞くと、
「一つ戻って、もうすぐバス来るよ」
と、ため息
Googleマップ🔎
車で3分
歩こう!
でも
甘かった急な坂道
何度も休憩した
目的地の神呪寺から降りてくる人とすれ違いながら
「神呪寺へ歩道」の看板
やったー!
新緑を歩き到着!




山のふもとに、こんな立派な寺Σ( ̄□ ̄|||)
拝観料金?いらない(◎_◎;)
さすが神戸
お金持ちの檀家さんが多いのだろう
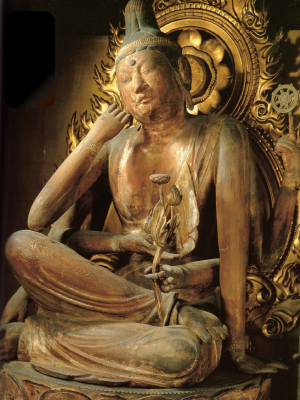
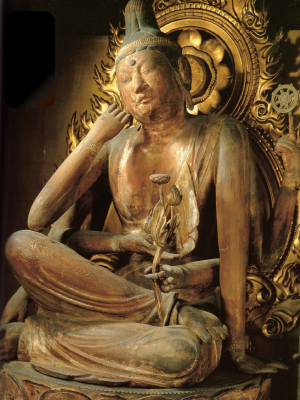


5月18日のみ拝観できる
如意輪観音さま
写真で、けだるそうな雰囲気に違和感を感じた




観心寺(大阪)如意輪観音
如意輪観音でも、大阪の観心寺(かんしんじ)とは、まったく違う雰囲気
実際に観ても?
でも引き込まれる魅惑的な像です
神呪寺(かんのうじ)




神呪寺は、兵庫県西宮市甲山(かぶとやま)町にある真言宗御室派の寺
甲山の山のふもとにあり、甲山大師(かぶとやまだいし)と呼ばれる
寺号の「神呪寺」は、「神を呪う」という意味ではなく、甲山を神の山とする信仰があり、この寺を神の寺(かんのじ)としたことによるという
「神呪」(じんしゅ)とは、呪文、マントラ、真言、「仏の真の言葉」という意味がある
神呪寺は、淳和(じゅんな)天皇のお后であった如意尼(にょいに)が、弘法大師(こうぼうだいし)(空海)に協力してもらい創建されたお寺
戦国末期、寺は織田信長に焼き打ちにされ、
豊臣秀吉の太閤(たいこう)検地で寺を半分に減らされると、僧たちは甲山を降りて暮らしたのが
寺から南東に3・5キロ
阪急電鉄今津線の門戸厄神駅付近
寺の名前をとった「神呪町」
寺は、それから約170年後、徳川5代将軍綱吉の母・桂昌院(けいしょういん)が200両を差し出すなどして神呪町付近に復元された後、
江戸中期の1749年、今の場所に再建された
如意輪観音菩薩像(にょいりんかんのんぼさつぞう)




重要文化財
平安時代
木造・彩色
像高 98.7㎝
5月18日のみご開帳になる秘仏です
神呪寺は、淳和(じゅんな)天皇のお后であった如意尼(にょいに)が、弘法大師(こうぼうだいし)(空海)に協力してもらい創建されたお寺
この像は、その如意尼をモデルにしている
左あしは、もとは下げられていたが、後世に今の形に変えられたそうです
融通観音とも呼ばれ
戦後から「金を融通してくれる」と言われて商業者の信仰もあつい
弘法大師坐像(こうぼうだいしざぞう)




重要文化財
鎌倉時代
檜(ひのき)寄木造り
像高 81.2㎝
弘法大師(空海)の58歳の姿
厄除大師として信仰され
甲山のお大師さまと親しまれている
アクセス
🚋電車と🚌バス
阪神電鉄「西宮」駅下車
駅の北側
阪神電鉄バス7番のりばから
「鷲林寺循環」に乗車する
循環バスは「西まわり」と「東まわり」があるが、真ん中ぐらいなので何れでもよい
「甲山大師前」で下車するとバス停から「神呪寺」まではすぐ